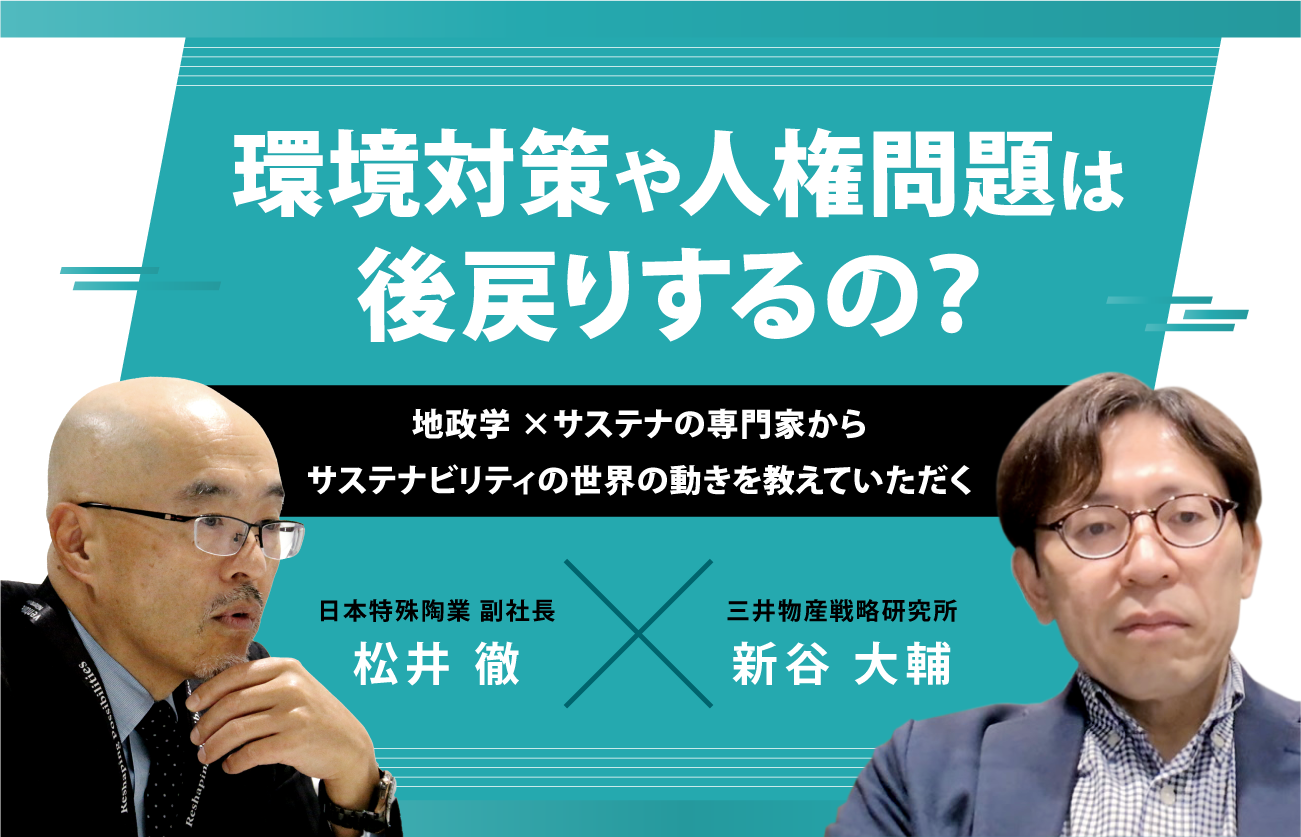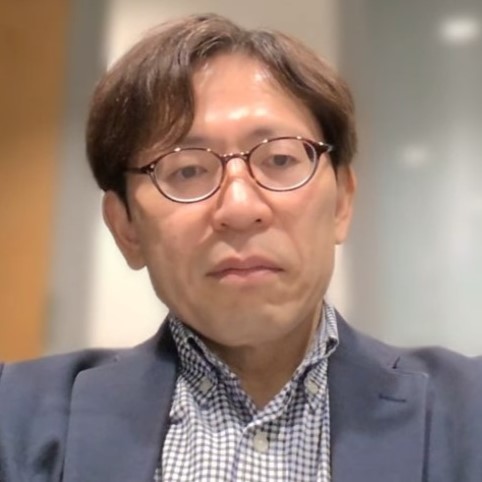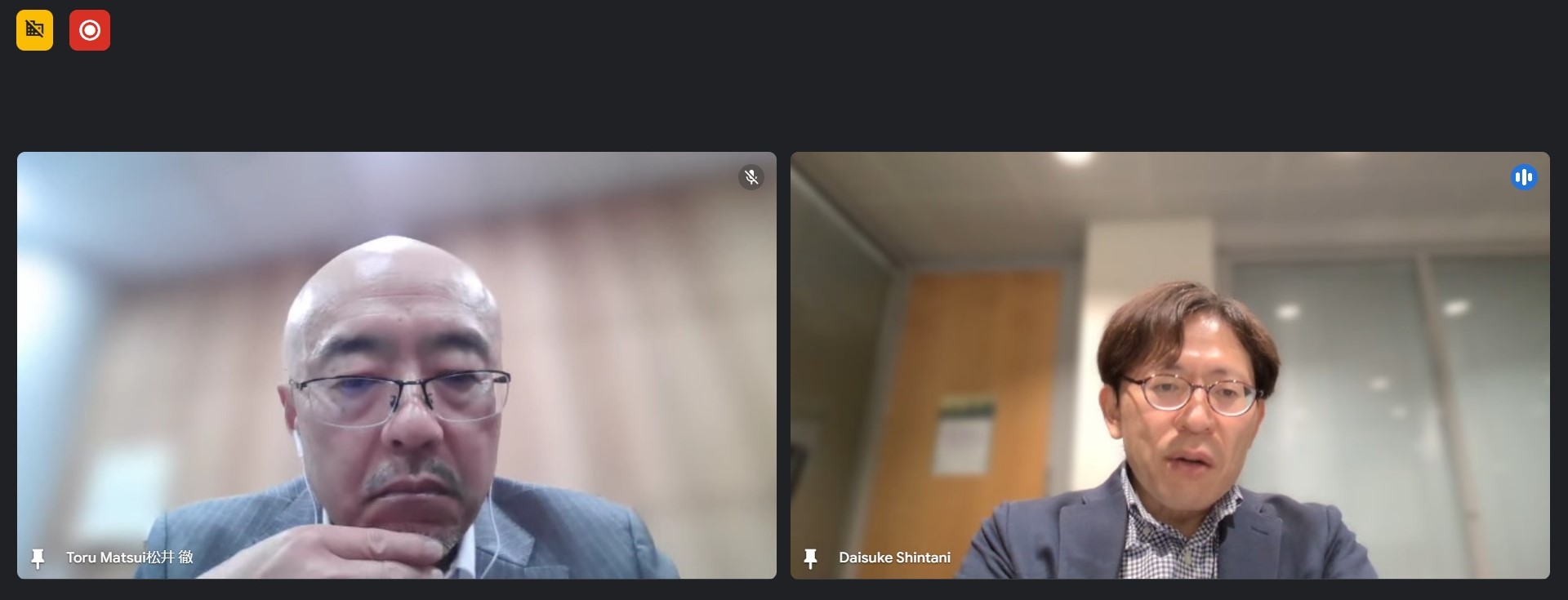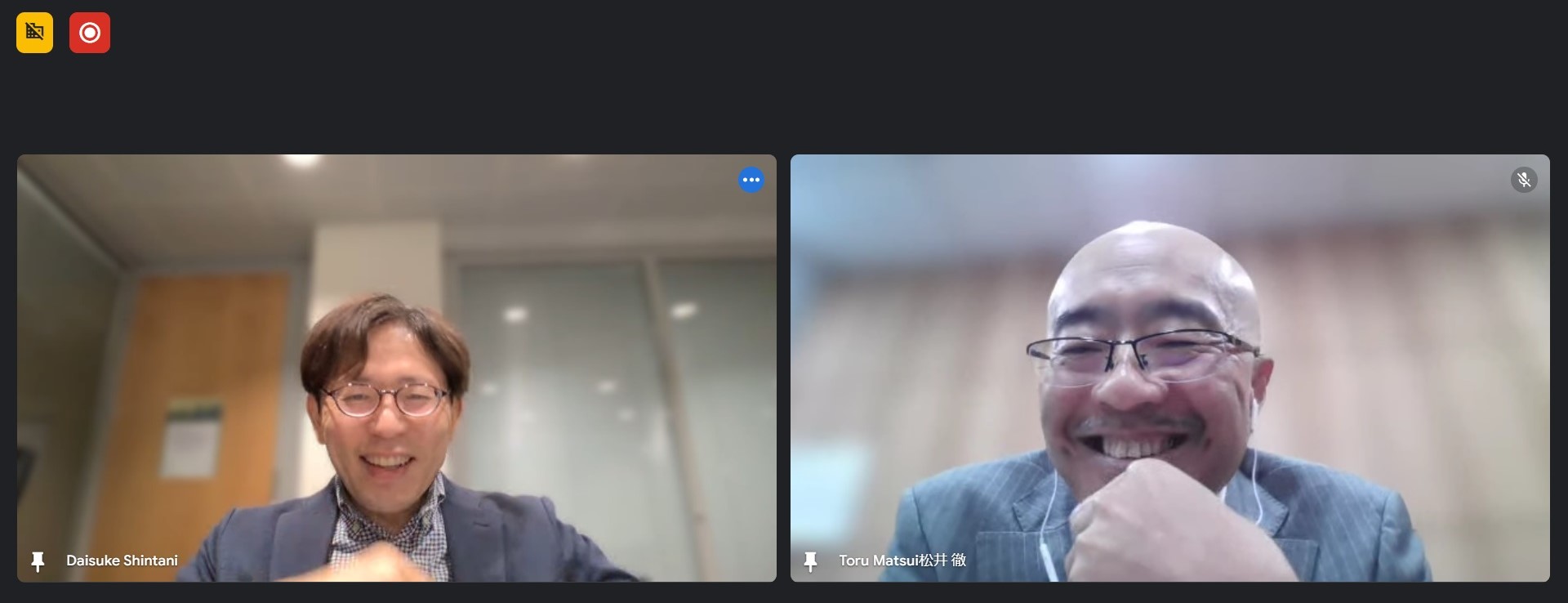Niterraグループは、地球の未来に貢献するため、世界各国でセラミックス技術をベースにさまざまな事業を展開しています。海外売上比率は約8割、拠点の数も国内32に対して海外は61カ所に置いています。
見回してみると、各国の経済は疲弊し、さまざまな社会問題を抱えています。それを打開すべくサステナビリティ(持続可能性)を高める企業活動に期待が寄せられてきましたが、「それどころではない」との声も聞こえます。一部の国や自治体では、「反サステナビリティ」「反ESG」の動きも出始めています。
今回、地政学とサステナビリティの専門家とのご縁をいただき、いまの国際情勢をどう理解できるのか、企業はどのような姿勢でそれに向き合うのか、を議論しました(対談は2024年12月に実施)。
いまの世界経済は、サステナどころじゃなくなっている? 松井
2024年は世界的な選挙イヤーでしたが、結果をみると自国の経済を最優先にするような保護主義がさらに広がりそうな予感を持っています。欧州でも経済情勢がよくない上に戦争の影が大きな影響を与えています。どこも将来の持続可能性より足元の経済を優先せざるを得ないようです。
松井徹
新谷
投資家目線の動きと事業会社の動きを分けて捉えたほうがいいと考えています。
新谷大輔さん https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/staff/1221473_10676.html
松井
アメリカの動きは象徴的に見えます。米国テキサス、フロリダ州などでは「反ESG法」が2023年ごろから成立され始めましたね。環境・社会・ガバナンスより金銭価値のみで投資判断をすべき、との流れが来ています。アメリカの情勢をどう見たらいいでしょうか。
新谷
強い愛国心が政治と直結することがあり、極端に見えているかもしれません。ただ、同じトランプ氏支持者の中でもどの側面を支持しているのかは千差万別です。第二次トランプ政権で、アメリカは石油やガスに力を入れると宣言しています。パリ協定からも離脱します。ただ、パリ協定の目標に従わないだけで、脱炭素をやめるわけではありません。トランプ氏は原子力や水力発電に積極的ですし、EV(電気自動車)産業をつぶすわけでもありません。中身を個別に見極めていく必要があります。
揺り戻しはあるけど、後戻りはしない 松井
欧州委員会の第1次フォン・デア・ライエン政権下では、グリーンディールとして温室効果ガスの実質ゼロ化を目指しました。高い目標を設定することで欧州企業の競争力を高めようとする意図を感じます。一方で、それが「グリーン疲れ」のようなものを生み、反動も高まっていると聞きます。
新谷
グリーンディールはとても野心的でした。しかし、足元では欧州各国の景気が悪く、移民が不況の原因とあらぬ非難を浴びる事態にもなっています。グリーンとバックラッシュ(反発)を組み合わせた造語「グリーンラッシュ」というキーワードを聞くようになりました。やりすぎへの反発です。2035年までに内燃機関車(ガソリンやディーゼルで駆動する自動車)の新車をゼロにする目標は撤廃か期限を延長するかの議論が進んでいます。欧州市場で販売や輸入される製品が森林破壊や劣化を引き起こしていないことを証明させる「欧州森林破壊防止規制(EUDR)」も域内から間に合わないとの声が多く、延期されています。
松井
気候変動への対応を企業に強く訴えかける環境アクティビストやNGO(非政府組織)たちは猛反発しているのではないですか? NGOからの働きかけはどう変化してきているのでしょうか。
新谷
環境アクティビストたちの動きや主張に変化はありません。欧州議会での議論の後退にかなりの危機感を抱いています。ただ、2024年6月の欧州議会選挙でEuropean Green Party(欧州緑の党、気候変動への対応を推進する議員の総称)が大きく議席を減らして、発言力が低下しています。加盟各国議会のグリーン議席も減少しています。その中でNGOたちが声を上げても、立法府がそれを受け取れない状況が広がっています。
松井
新谷
逆行する動きは一切ありませんし、これからもないでしょう。ただ、足元の景気も悪く、すぐそばでウクライナや中東での戦争があり影響を多大に受けています。化石燃料に傾倒するとは言えないまでも、一部を先延ばしする政治戦略が働きやすいのも事実です。過去と比較すればマイルドに変化が起きていくと予測されます。
産業を育成して競争力を高めていく作戦の実行期に 松井
欧州では、反ESGというより「緩ESG」という感じですね。私たちのような事業会社は、だからといって油断しているわけにもいきません。グリーン領域にビジネスの成長機会がたくさんあるわけですし、それが地球の未来にもつながりますから。
新谷
2024年12月からの欧州委員会第2次フォン・デア・ライエン政権では、①脱炭素化、②安全保障、③競争力強化を柱とする戦略を打ち出しています。25年2月に公表が予定されている「クリーン産業ディール(Clean Industrial Deal)」を柱に、クリーンな産業を育成することによるEUの競争力強化を高める計画です。次の5年は第1次政権下の5年で構想したことの「実行期」と位置付けています。具体的な政策はこれからですが、目標を下げたり先延ばししたりすることが多少あっても、クリーン産業の力を高めるための新たなルールや補助金、ファンド制度がでてくるはずです。成長産業をつくるために経済的な補助をする、という方針の中で、企業がどこに伸びしろを見出すのかが問われていきます。
松井
サーキュラーエコノミーへの移行も進んでいきますよね。そのほか、欧州委員会が注目している環境キーワードはありますか?水もかなり力を入れると聞いています。私たちも水に関してはここ数年で認識を新たに取り組んでいるところなのです。当社グループの水使用量の把握と削減はもとより、水リスクが与える影響の査定と対策、水質浄化への自社技術の利活用などを進めています。
新谷
サーキュラーエコノミーは、それを推進する行動計画を定めて継続して遂行中です。グリーンラッシュの影響を受けることはほぼない大きなテーマの一つであり続けます。水は、「ウォーター・レジリエンス」(水の回復力:水量や水質、水へのアクセスなど水に関する問題を軽減する概念)をEUでも取り入れ、2029年までの政策の柱である「戦略アジェンダ2024-2029」の中にしっかり位置付けられています。EUにとっても、2024年に大きな干ばつにあい、深刻で身近なテーマになっています。競争力を高めるために水の回復力をつけないといけないわけです。例えば、農業における水だったり、有機フッ素化合物(PHAS、ピーファス)のような物質の水への溶け込みだったりの問題があります。AIやデジタル技術を絡めて、水の保全や確保、安全保障を強化する動きもみられます。
私たちは、移行期の真っただ中にいる 松井
今後のエネルギー転換についてはどのような流れで進んでいくのでしょうか。世界的に水素にも注目が集まっていますが、水素の供給にかなりの補助金をつけても買い取り価格がつかないのは、需要が足りていなかったり、コストが割高だったりするからですよね。
新谷
その通りです。需要が足りていません。アフリカ諸国を含めて水素をつくる国はたくさんでてきていますが、使うと言っている国は少ないです。いまはどこに突破口があるかを見極める段階なのでしょう。歴史を振り返ると、石炭から石油に置き換わった時にはコストが逆転したと同時に戦争があり、必要に迫られていた経緯があります。いまは石油が市場として成り立ちコストも安い中で、再生可能エネルギーに切り替えるほどの需給バランスが成立していません。足元の需給バランスを踏まえた上で、各国と連携しながらエネルギー安全保障政策や依然として影響力のあるEUのルールメイキング、脱炭素やクリーンテックの技術革新のスピードが異常に速い中国の動向も注視しておきたいところです。植物などの生物資源を原料として製造する再生可能な燃料「バイオ燃料」あたりは、いまの現実的な落としどころなのかもしれませんね。ここロンドンでは見かけませんが、東南アジアや南アメリカなどで車などの燃料として導入が進んでいます。
松井
混沌とした中で、私たちは移行期にいるのかもしれませんね。お話を聞いていて、幅広く選択肢をもって見極めながら進んでいく必要を改めて感じました。
新谷
トランジション(移行期)にいるからこそ、新たな動きに呼応する産業や企業が伸びていくわけです。
松井
何か発火点になるかもよく分からない時代だからこそ、選択肢を複数もって経営をする必要があるわけですね。未来の理想像を描いて仲間を増やすこともしながらも、現実的な解に積極的にかかわることもトランジションを加速させる手であり、企業の伸びしろなのだとも認識しました。
新谷
外から拝見する限り、御社のサステナビリティの取り組みは着実なものだと感じています。課題感も明確に把握しており、悩みながら進んでいることも分かります。一方で、本当の先進企業がどんなことをやっているのかをみると、「自分たちはこの分野でトップランナーになる」と宣言しています。業界で横並びに取り組むのではなく、トップを目指す。御社にも自分たちがルールをつくる側にまわるという意気込みを期待したいです。